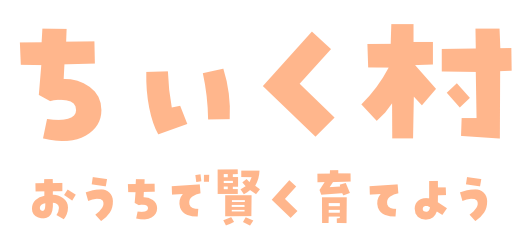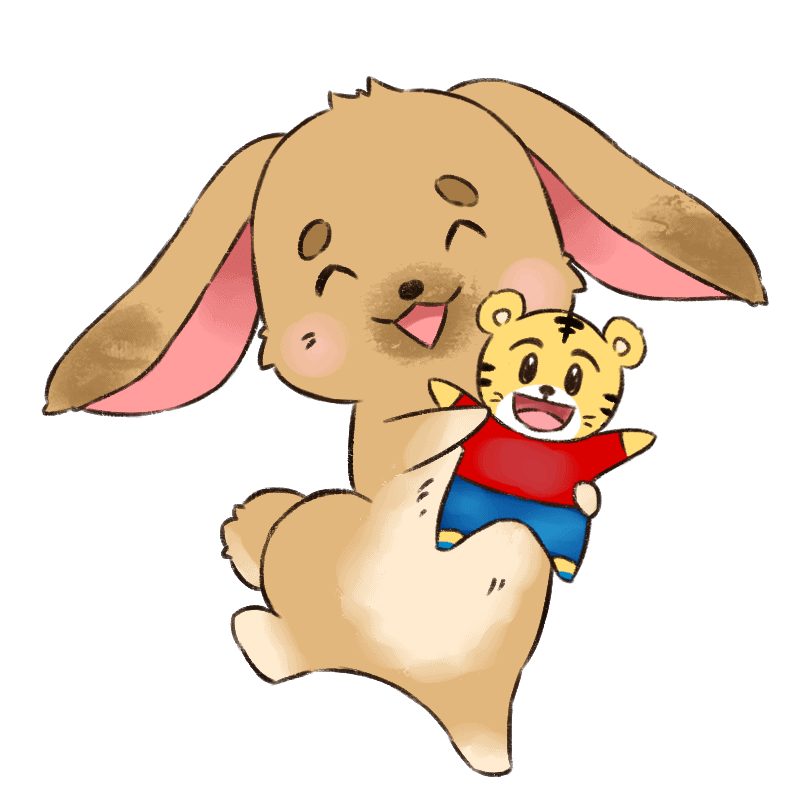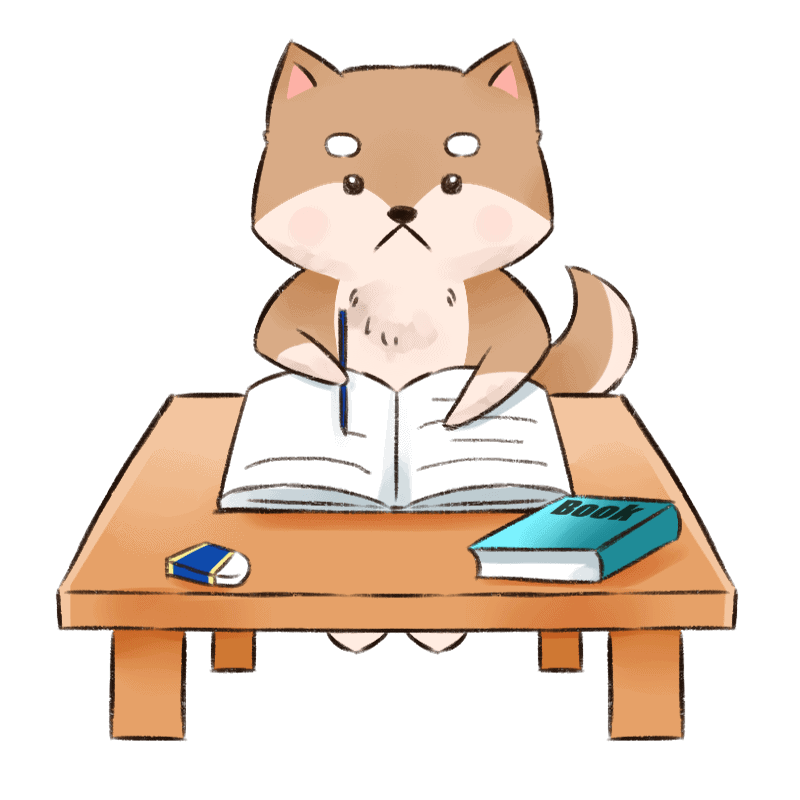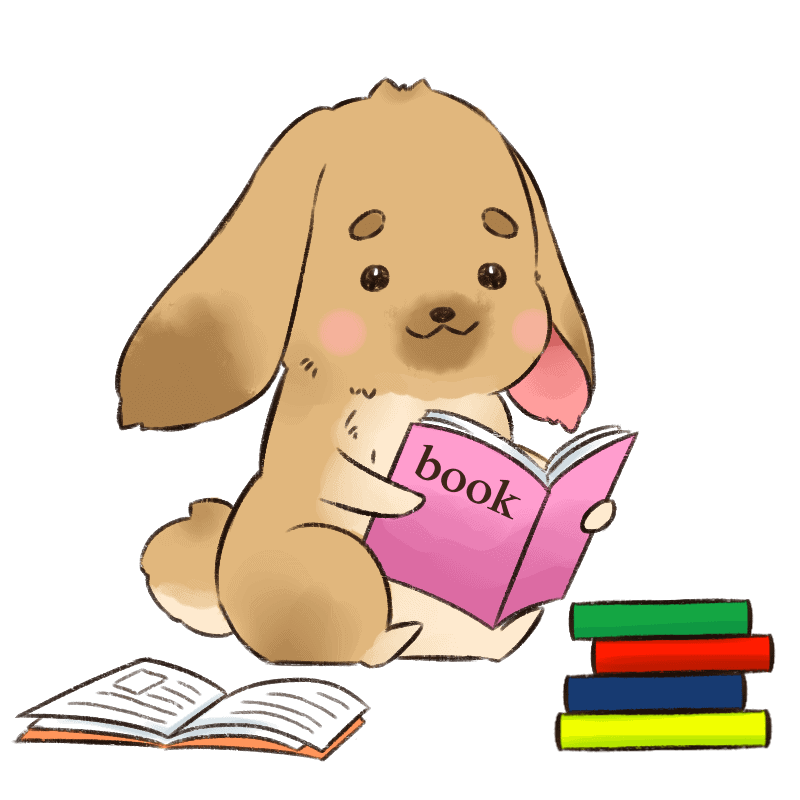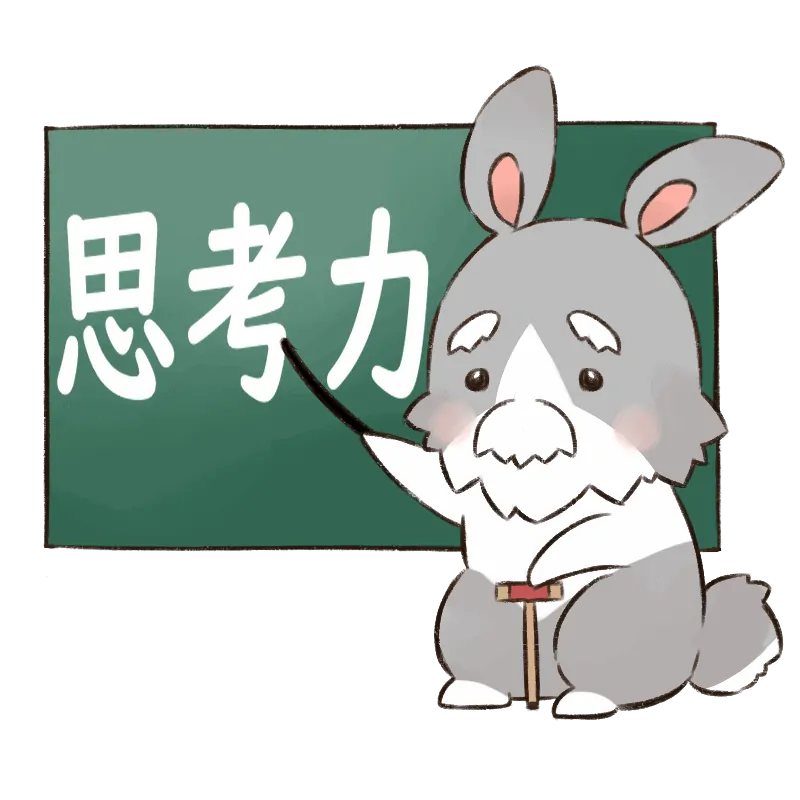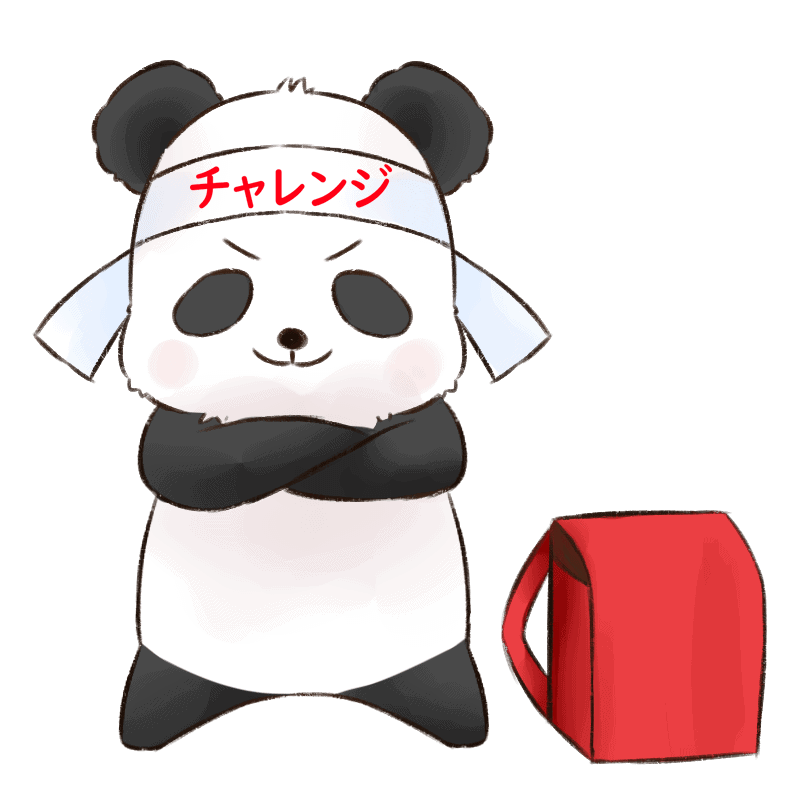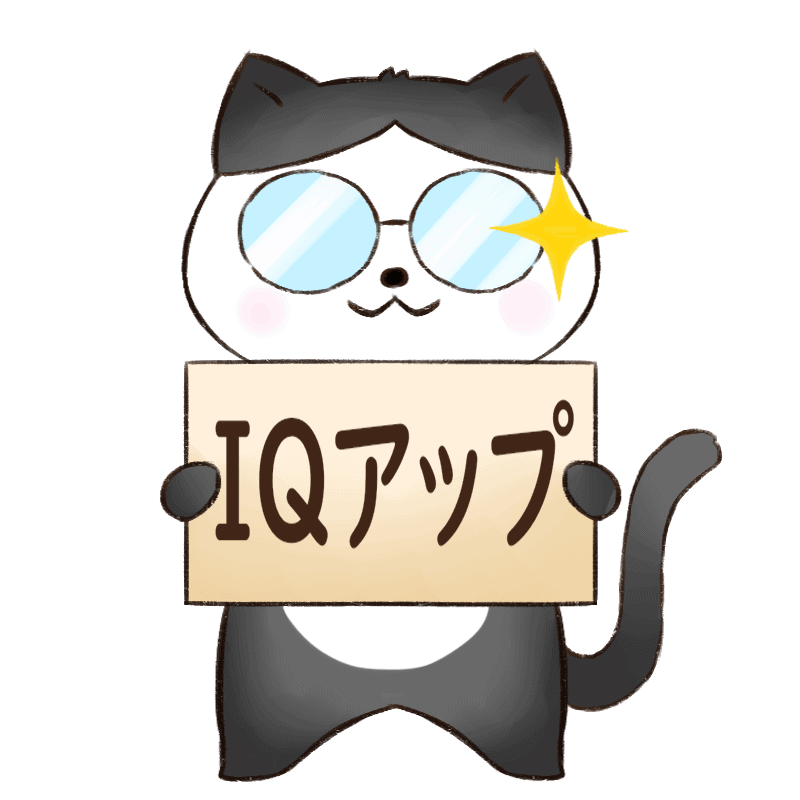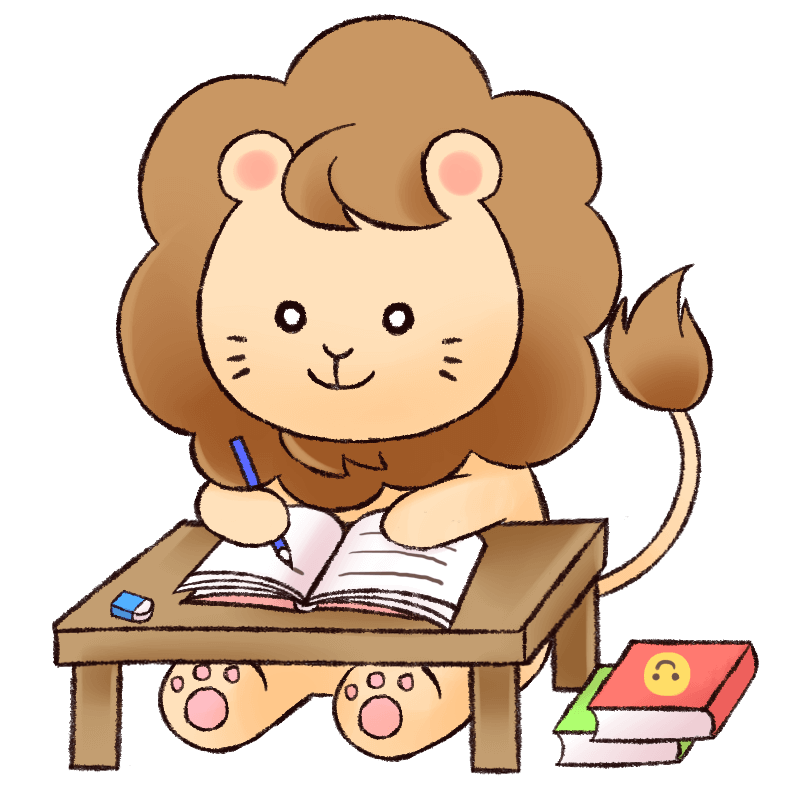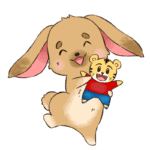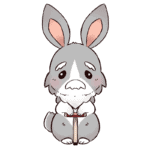小学生は放課後に何する?共働き世帯の過ごし方や遊ばせたくないときの工夫も紹介
小学生は放課後に何することが多いのか、共働き世帯の過ごし方などをまとめました。
小学生になると、帰宅が早い日があったり、子供たちだけで遊びに行きたくなったりと、放課後の過ごし方がガラッと変わって戸惑いますよね。
放課後には何するのがいいのか、遊ばせたくないときはどうするべきか、悩む親御さんも多くみられます。
そこで今回は、小学生は放課後に何することが多いのか、傾向や選択肢について解説。小学生の保護者が放課後に関して悩みがちなこともまとめたので、ぜひ読み進めてみてください。
小学生は放課後に何する?
今の小学生は放課後に何するのかというと、以下のように多様な選択肢があります。
- 家でゆっくり過ごす
- 友達と家や児童館で遊ぶ
- 公園で外遊びする
- 学童保育を使う
- 習い事へ行く
- 課外活動をする
令和の小学生は、学童保育へ行ったり習い事へ向かったりと、忙しいスケジュールの子も多いです。
その一方で、急に早くなった帰宅時間に戸惑う親御さんも多く、まさに小1の壁と言えるかもしれませんね。

家でゆっくり過ごす
小学生が放課後何するか1つめは、家でゆっくり過ごすことです。学研教育総合研究所の調査によると、放課後に過ごすことが多い場所は自宅が断トツです。
放課後、どこで遊ぶこと(過ごすこと)が多いかをきいたところ、「自宅」(73.8%)が突出して高くなり、「友だちの家」(23.6%)、「公園・運動場」(22.8%)、「学童」(17.1%)、「習い事」(13.9%)が続きました。学年別にみると、1年生と2年生では「学童」が2位、3年生では「公園・運動場」が2位、4年生以上では「友だちの家」が2位でした。(引用元:小学生白書Web版/2026年11月調査)
まだまだ低学年のうちは、学校の授業と通学だけで疲れてしまうのも当たり前ですよね。家に帰ってきたら、おやつを食べて宿題をしたあとは、テレビを見ながら過ごすという子が多いかもしれません。
また、高学年になってくると、家に帰ってきてから、集合時刻を決めておいてオンラインで友達とゲームをするという子もいますよ。
普段学校で頑張っている分、放課後は家でのんびりと過ごし、早めに明日の準備を済ませてしまうのも良いですね。
友達と家や児童館で遊ぶ
小学生が放課後何するか2つめは、友達と家や児童館など、屋内で遊ぶパターンもあります。
だんだんと約束も上手になってくるので、友達の家に集まったり、逆に誰かの家ばかりに負担にならないように、児童館のような公共施設で遊んだりすることも。
また、児童館や小学校などで遊ぶようにしていますが、同じ学校の上級生も遊びに来るので自然と一緒に遊ぶようになりました。親としても、必ず近くに大人がいる場所なので安心して遊びに行かせることができています。(引用元:Z会)
天気の悪い日の放課後や、真夏や真冬など、外遊びができないときの選択肢としても多く挙がります。
ただし、特定の子の家にばかり集まるとトラブルが起きることもあるため、親御さんとしては少し気がかりな面もあるかもしれません。

公園で外遊びする
小学生が放課後に公園などの屋外で遊ぶのも定番ですよね。家に帰って、宿題を済ませてから遊びに行くパターンが多いかもしれません。
親御さんと決めた時間まで、と約束してから出かけて、外遊びを楽しむ子は多いです。
放課後に公園で遊ぶ約束をしてきますが、「遊べなかったら行かない」「15分待っても来なかったら帰る」とお互い無理なく約束しているようです。「絶対」という縛りがないので、気持ちも楽みたいです。(引用元:Z会)
公園なら似通った年齢の子が集まったり、広いスペースがあったりするので、有り余った体力を消費してきてもらうのにもぴったりです。
勝手に道路や家の外で遊ばれるよりも、よっぽど心配も少ないので安心ですね。
学童保育を使う
共働き世帯が小学生のお子さんがいる時、学童保育を使う方がほとんどです。
学童保育といっても、公的なものから民間まで、今は多彩な種類・特徴を持った学童サービスがあります。
外遊びの機会を大切にしている教室や、英語学習に力を入れている学童など、子供に経験させたいことを軸に学童選びをするのもよいかもしれません。

なお、学童保育で宿題を済ませてくることがほとんどですが、夏休みなどの長期休みは学童に持っていける紙形式の通信教育やドリルを準備する親御さんも多いですよ。
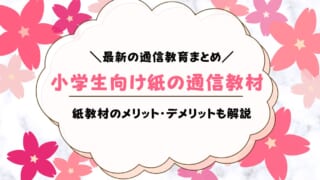
習い事へ行く
放課後習い事へ行く小学生も多いです。スイミングや英会話、習字や公文など、小学生の定番の習い事を複数掛け持ちしている子もいます。
ベネッセの調査によると、小学生が有料の習い事をしている率は約70%とのこと。3人に2人が何かしらの習い事をしている計算になります。
有料の習い事をしている小学生は全体の70%と、およそ3人に2人が習い事をしているという結果に。また、有料の習い事をしている小学生のうち、習い事が1つの小学生は45.2%。2つ以上習い事をしている小学生が54.7%と半数を超えています。(引用元:ベネッセ教育情報)
習い事がある日はスケジュールがタイトになりがちなので、自宅学習においては、スキマ時間をうまく使えるようなデジタル教材が好まれる傾向があります。
また、中学受験を視野に入れている子は、早くから学習塾に通わせるご家庭も多いですが、習い事に関しては親が時間を確保しやすい土日に予定を入れているというケースがよく見られるようです。

課外活動をする
小学生が放課後何するか6つめは、スポーツ少年団やボランティア、地域活性化などの課外活動をすることです。
小学生になると、友達や兄弟がやっているからと、スポーツ少年団や和太鼓などのサークル、地域の有志活動に参加する子も増えてきます。
スポーツ少年団の活動は、学校時間や家庭時間を除く自由時間に行い、活動拠点は学校内ではなく、地域社会の中にあります。また、スポーツ少年団の主活動であるスポーツ活動は競技スポーツばかりではなく、発育発達段階を考慮したスポーツ活動のほか、学習活動、野外活動、レクリエーション活動、社会活動、文化活動など幅広く捉えています(引用元:JSPO日本スポーツ協会)
異年齢交流の機会でもあるため、積極的に参加してみるのも良いですね。
違う校区の子とコミュニケーションをとることもできるので、視野が広がって友達付き合いの上手な子になってくれるかも。

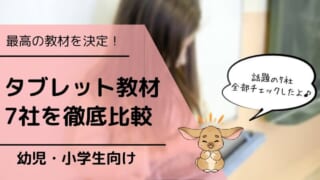
【共働き世帯】小学生の放課後の過ごし方
つぎは共働き世帯にもっと焦点を当てて、小学生の放課後の過ごし方を見てみましょう。
低学年の場合は学童保育、高学年の場合はお留守番というパターンが多いようです。
小学校低学年:学童か習い事
先述の通り、共働き世帯の小学生のうち低学年の子は、放課後に学童保育や習い事に通う子が多いです。
通わせる人が多くなったせいか、学童の形態も多様化。サービスによっては、直接子供を小学校に迎えに行ってくれる学童や習い事もありますよ。
たとえば、明光義塾が運営する民間学童「明光キッズ」などでは送迎サービスも提供しています。
明光キッズでは3つの送迎プランをご用意しています。全ての送迎プランにおいてコーチが寄り添い、送迎中は細心の注意を払いお子さまの安全を確保します。送迎方法は徒歩・公共交通機関・専用車輌を利用して行います。(引用元:明光キッズ)

なお、低学年のうちは、リモートワークや在宅の仕事を選ぶ親御さんも少なくありません。時短勤務制度を使ったり、パートでの就労を選んだりする保護者も。
授業が早く終わる分、放課後の時間が長い傾向にあるため、保護者も柔軟な働き方が求められる時期でもありますね。
小学校高学年:お留守番か塾や習い事
共働き世帯の小学生のうち、高学年になってくると、お留守番も放課後の選択肢に入ってきます。
今はWebカメラや子供用GPS、通信手段も多数あるため、保護者が仕事中でも帰宅したかどうかをチェックすることができます。だからこそ、これを選択しに入れているご家庭は多いのでしょう。
また、小学校3~4年生からは中学受験に向けて通塾や通信教育など、お勉強の量を増やしていくご家庭も多いです。

小学校高学年は理科・社会など教科数も増え、難易度もアップしてくるので、勉強につまづきやすくなってくるタイミングでもあります。
中学受験の有無にかかわらず、進学前に通信教育や塾などの学習をサポートする仕組みを強化して、放課後を有効活用するご家庭もありますよ!

小学生の親が放課後何するかで悩みがちなこと
通園だけで良かった未就学児と異なり、小学生が放課後何するかというのは、保護者にとっては非常に悩ましい問題ですね。
交友範囲も広がり、小学校で急にいろいろな価値観に触れて、保護者の管理下ばかりにもいられない時期でもあります。
また、学年が上がるにつれて一人で行動する場面も多くなっていきます。子供が大きくなったからといって、安心してほかっておくこともできません。

子供だけで留守番
親御さんが放課後に最も心配なことの1つが、子供だけでの留守番です。親の管理下でないと気が大きくなって、ついつい勝手なことをしてしまいがち。
きちんと家の中に入れるか、カギをかけられるか、火元に近づかないかなど、心配は尽きませんよね。
また、勝手に友達を家に入れてしまわないか、逆に友達の家で失礼なことをしてしまわないか、といった対人トラブルに関しても悩みがちでしょう。
だからこそ、あらかじめルールを作り、共有しておくことはもちろん大切ですが、仕組みとして一人で長時間過ごさずに済む、または時間をつぶせる工夫も必要かもしれません。

友達の保護者の連絡先
親御さんが放課後の過ごし方で、特に友達と遊ばせるときに悩みがちなことは、相手の保護者の連絡先を知らないことです。
とくに小学校高学年になると、下校途中で勝手に友達と「後から遊ぼう」と約束してきたり、「休みの日に集まろう」と決めてしまったりして、トラブルになりがち…。
低学年のうちは、子ども同士での約束は難しいかもしれません。わが家も「遊ぶ約束した!」と帰ってきても「いつ」「どこで」が決まっておらず、結局お互い習いごとで予定が合わず、遊べる日がありませんでした。(引用元:Z会)
相手の連絡先を知っていればスムーズに誤解を解くこともできますが、上記のように約束をすっぽかしたことになってしまう心配があります。

お礼を言うタイミングも逃しやすく、トラブルがあったときに謝る手段も限られてしまいますよね。
初回の待ち合わせには保護者もついていき、相手の親御さんと連絡先を交換することを心掛けるのがよいかもしれません。
一人で遊びに行きたがる
だんだん自我が強くなってくる小学生の時期は、「一人でも行ける」「お母さんは来ないで」など、放課後の過ごし方にもハッキリと自己主張してくる場合が多いです。
「友達は一人で行動してるのに」と、別のご家庭と比べて自由を求めることもあるでしょう。
我が家は我が家、とルールを決めることも大切ですが、成長に応じてケースバイケースで制限を緩めていくことも必要です。

まずは、門限や外出範囲、交通マナーなど、最低限のルールを守ることに重きを置きましょう。
たとえば、ベネッセの調査によると、小学生の場合は17時頃の防災無線に合わせて帰宅、というルールのご家庭も多いようですよ!
学年によって門限は異なりますが、小学校を中心とした多くのご家庭で17~18時に設定している様子でした。その理由は、地域の防災無線やアナウンスが鳴る時間だからだそう。時計がない場所でも時間がわかる放送は、帰る時間を決めるよい目安になっているのかもしれませんね。(引用元:ベネッセ教育情報)
このように最低限のボーダーラインを決めておくと、叱るべきこと・許容しても良いことの判断がしやすいかと思います。
あまりにも細かいことは少しずつ目をつぶる勇気を持ち、親子の信頼関係を維持しながら、子供の安全を守りましょう。
ダラダラ過ごす時間
低学年のうちは、疲れて放課後にゆっくりするのも致し方ありませんが、年齢があがってくると、体力が十分に有り余っている子も出てきます。
体力が有り余ってるにも関わらず、毎日ダラダラとゲームをして過ごす様子を見ていると、悩ましく思う親御さんは多いのではないでしょうか。
たとえば、学研総合研究所の調査結果によると、放課後の過ごし方のうち、ゲームや動画視聴など自宅で過ごす時間が多めにあがっています。
放課後の過ごし方について、どのようなことに、どのくらいの時間を費やしているかをきいたところ、「テレビ視聴」が最も長く平均は80分となり、以下、「ゲーム」58分、「インターネット(動画視聴など)」58分、「塾・習い事」53分、「宿題・勉強」46分、「友だちと会話」46分、「外遊び」44分、「本・まんがを読む」32分、「友だちとメッセージのやり取り(LINEなど)」19分と続きました。(引用元:小学生白書Web版/2026年11月調査)
かといって、家計への負担もありますから、「なんとなく暇そう」という理由で通塾や習い事を増やすのは得策ではないかも。
たとえば、コストが低い通信教育を取り入れたり、本人が興味を持ちそうな習い事や課外活動を始めてみるのがよいでしょう。
ダラダラ過ごす時間を有効活用したいなら、それを上回る関心を惹くサービスを選ぶ必要があります。


小学生に放課後あまり遊ばせたくないときの工夫
小学校が終わった後の放課後あまり多くの時間遊ばせたくないとき、または遊びだけで済ませたくないときの工夫を紹介します。
小学生にとって遊びも確かに大切ですが、いずれ中学生になることを考えると、ONとOFFのメリハリをつける練習も必要ですね。
また、トラブルを防ぐために遊びの時間の比重を減らしたい、という場合もあるでしょう。そんなときにできる対策を3つ紹介します。
守るべきルールを決める
大前提として、放課後遊ばせたくないときには、最低限守るべきルールを決めておき、共有しておく必要があります。
小学生に対して全く遊ばせない、というのは難しいです。あまり遊ばせたくないなら、短めの門限を設けるなどの工夫が必要でしょう。
あまりに厳しすぎると、反発して反抗期に突入したり、親に嘘をつくようになったり、友達付き合いが難しくなるリスクもあります。
門限や遊べる曜日、外出してよい範囲など、守るべきルールを家族みんなで決めて共通認識にしましょう。
たとえば友達の家に行くなら、「誰の家に何人で集まるのか」「勝手に家のものを触らない」「〇時になったら帰宅する」「親御さんと連絡先を交換する」など、トラブルを防ぐためのルール決めをしておけば良いのではないでしょうか。

宿題や通信教育をしてからにする
放課後に遊びっぱなしを避けたければ、宿題や通信教育など、何かやるべき課題を済ませてからしかダメ、と徹底するのをおすすめします。
明日の準備まですべて終わらせてから遊びに行きなさい、とゴールを決めることで、放課後の貴重な時間をダラダラ浪費せずに済みます。
夜ご飯が終わっても宿題を済ませられていない、寝る時間が遅くなる、朝に慌てて終わらせる…このような行き当たりばったりの生活が定着してしまうと、学習がそもそも習慣化されません。
ちなみに宿題より通信教育のほうが管理がラクです。たとえば、小学生向けの通信教育は、1単元が短めに設定されているものが多いです。スマイルゼミのように「今日のミッション」とやるべき単元をおすすめしてくれる機能も便利ですよ。
とくにおすすめなのは、「きょうのミッション」を活用されることです。「きょうのミッション」では、無理なく理解が進むように取り組めるように誘導するだけでなく、苦手な教科が残ってしまわないように、各教科をバランスよく取り組めるようにしています。(引用元:スマイルゼミ)
毎日やるべき教材に迷わない上に「これだけ済ませたらいいよ」とルール決めしやすいのもポイント。タブレット学習なのでゲーム感覚で楽しく取り組めます。


遊ぶのは土日にメリハリをつけて
放課後がかなりタイトなスケジュールなら「遊ぶのは土日」とメリハリをつけるのも良いですね。平日は宿題や次の日の準備、家庭学習に振り切って、休みの日は思いっきり遊びに使ってみてはどうでしょうか。
特に共働き世帯のフルタイム勤務では、平日は子供だけで遊ばせるのにも限界があるので、平日は学童でお友達と触れ合うだけにとどめて、週末は仲の良いお友達と家族ぐるみで遊ぶというのもアリです。
保護者も平日ほど時間を気にせず遊ばせられますし、子供もリフレッシュできる良い週末の過ごし方になるのではないでしょうか。
【まとめ】小学生が放課後何するか迷ったら学びを足すのもアリ
今回は小学生は放課後に何するのが多いか、保護者は子供の放課後にどんな悩み事があるのかをまとめてみました。
小学生が放課後に何するかというと、自宅でゆっくりする子もいれば、公園や友達の家に遊びに行ったり、習い事や学童、課外活動をしたりと様々な選択肢があります。
しかし、一人で遊びに行ってほしくない、ダラダラ時間を浪費してほしくないと、放課後の過ごし方に関する保護者の悩みは尽きません。
もし放課後何するか迷ったら、まずは無理のない程度の学びを足してみるのもおすすめですよ。
遊びと勉強のバランスをとる練習をしておくと、いずれ中学生になったとき自学自習できる心の強さが身につくので、ぜひ検討してみてくださいね。


我が家で1番活躍してるのは
「スマイルゼミ」
20教材以上を検討して
毎日自主的に取り組み
お勉強するのが
好きになってくれたのは
スマイルゼミのおかげでした
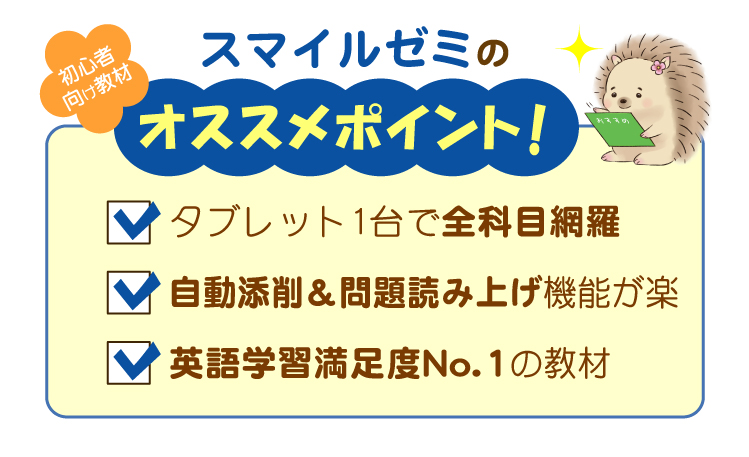
ちいく村限定の
キャンペーンコードも配布中
お得に入会可能です。
ちいく村限定の1,000円特典付き
キャンペーンコードは
スマイルゼミの特設サイト![]() から
から
資料請求でGET
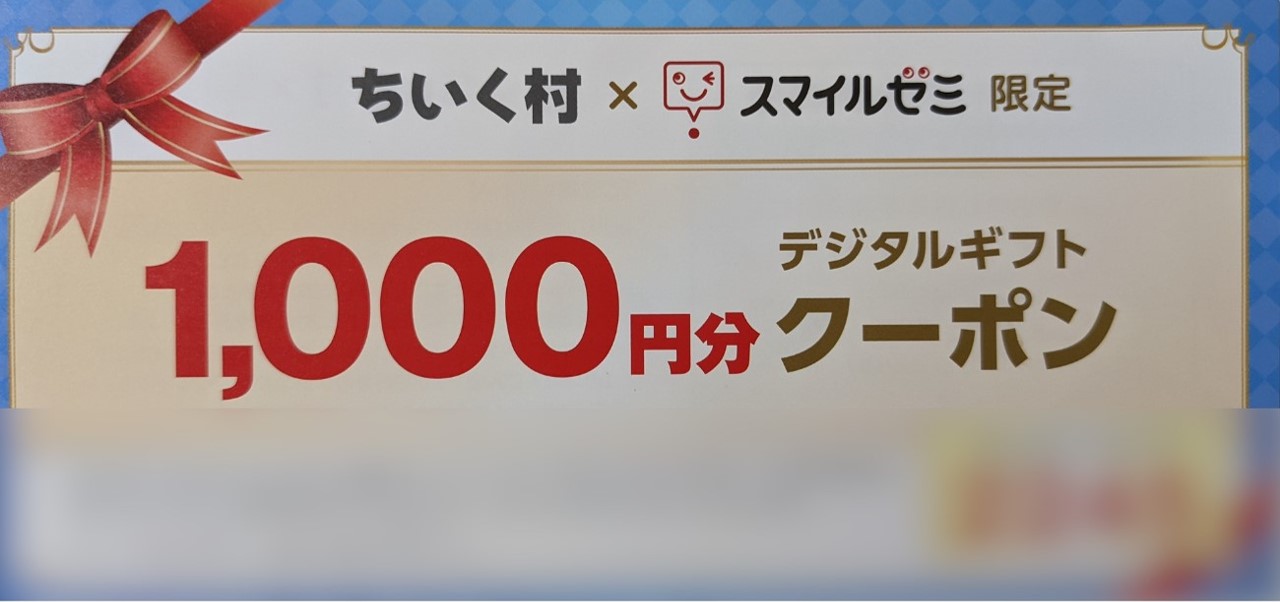
1,000円の紹介特典や
初月受講費無料キャンペーンとも
併用可能です
スマイルゼミに
1番お得に始める方法なので
ぜひチェックしてみてくださいね💕
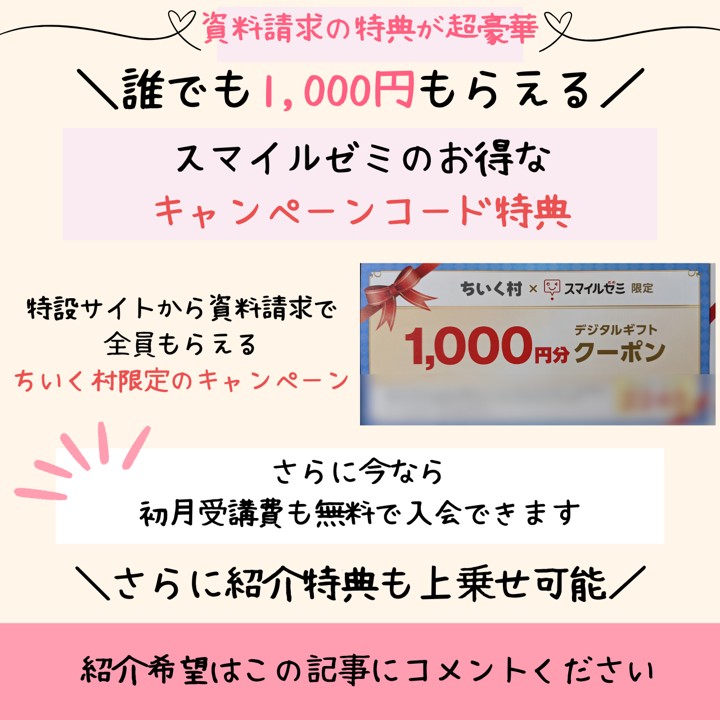
資料請求で安く入会
スマイルゼミの特徴
タブレット1台で全科目学べる
教材が溜まらない&自動添削が楽
英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/
特設サイトからの資料請求でギフト券GET